| 「政治のガバナンス・マネジメントとは ~関西「望年会」を開催~」 | ||
 12月22日、京都でも「青年学生『日本再生』読者会」の学生を中心に「望年会」を開
催。大雪によって交通機関にも支障が出たため、環整連のみなさんをはじめ、出席で
きなくなった方もいたが、学生・若い世代を軸に、歴史に学び、将来世代に責任をと
る情報(インテリジェンス)力や想像力とはなにか、人として生きるとは何かを問い
会う交流の場となった。 12月22日、京都でも「青年学生『日本再生』読者会」の学生を中心に「望年会」を開
催。大雪によって交通機関にも支障が出たため、環整連のみなさんをはじめ、出席で
きなくなった方もいたが、学生・若い世代を軸に、歴史に学び、将来世代に責任をと
る情報(インテリジェンス)力や想像力とはなにか、人として生きるとは何かを問い
会う交流の場となった。
戸田代表は、「感性の共有なくして深いメッセージは伝わらない」と、ここまでの 流れを総括。違う世代の感覚や気持ちの共有を通じたコミュニケーション能力が政治 のガバナンス力の基礎であり、マネジメント能力に通じる。「縦軸=歴史軸」と「同 時代の関係=横軸」をしかととらえること、国民主権である以上、様々な生き様の違 う国民が国や社会のありようをどのように考えるかをとらえること、とくに脳を鍛え る青年期に自分の目線からわかる部分だけでなく、このような問題設定の仕方を学ぶ ようにと示唆があった。また、政治権力闘争上の問題を「理論的正しさ」一般で総括 してはならず、政治権力闘争において「人の情」をつかむことの重要性があらためて 強調された。
最後に、参加学生13名全員が発言。政治社会上の問題意識と将来の進路選択につい
て交々述べられ、長尾敬同人(民主党・大阪14区総支部長)からの、自ら捲土重来を
期す決意と青年学生への檄で中締めとした。 同人・杉原卓治 | ||
| 「恒例の『望年会』、大いに盛り上がる」 | ||
 12月6日、恒例の「望年会」を、私学会館(アルカディア市ヶ谷)にて開催。
昨年同様、約二百名が参加し、大いに盛り上がった。 12月6日、恒例の「望年会」を、私学会館(アルカディア市ヶ谷)にて開催。
昨年同様、約二百名が参加し、大いに盛り上がった。昨年は都議選候補として決意を述べた会員の多くが、今年は新人議員としてそれぞれ の抱負を述べた。  望年会という名称は、十五年くらい前から使用しているが、昨今はあちこちにパクら
れてもいる。結構なことではないか。「忘れて」しまうより、きちんと総括すべきは
総括して新しい年を展「望」しよう。 望年会という名称は、十五年くらい前から使用しているが、昨今はあちこちにパクら
れてもいる。結構なことではないか。「忘れて」しまうより、きちんと総括すべきは
総括して新しい年を展「望」しよう。
 今年の司会は、同人会員の鈴木烈さんと田の上郁子さん。鈴木さんは十一月の葛飾区
長選に挑戦、惜敗したが、次を目指して来年は「バッジをつけない主権者」として活
動すると表明。田の上さんは江戸川区議、〇七年もトップ当選をめざしてがんばる。 今年の司会は、同人会員の鈴木烈さんと田の上郁子さん。鈴木さんは十一月の葛飾区
長選に挑戦、惜敗したが、次を目指して来年は「バッジをつけない主権者」として活
動すると表明。田の上さんは江戸川区議、〇七年もトップ当選をめざしてがんばる。
 主催者あいさつは、花輪都議。都議会政調会長代理として、柿沢未途・政調会長、初
鹿明博・幹事長代理とともに、新人二十人、総勢三十五人の都議会民主党を「戦う集
団」としていくとあいさつ。都議選マニフェストのおかげで、三十五人が同じ方向を
向いて、課題を分担していく指針ができた。 主催者あいさつは、花輪都議。都議会政調会長代理として、柿沢未途・政調会長、初
鹿明博・幹事長代理とともに、新人二十人、総勢三十五人の都議会民主党を「戦う集
団」としていくとあいさつ。都議選マニフェストのおかげで、三十五人が同じ方向を
向いて、課題を分担していく指針ができた。柿沢都議、初鹿都議のほかにも、多くの都議がそれぞれ力強くあいさつ。(増子都 議、伊藤まさき都議、伊藤悠都議、野上都議、原田都議、吉田都議、猪爪都議、酒井 都議/順不同)  戸田代表のあいさつでは、コミュニケーション能力の大切さが強調された。今回の総
選挙は、構造社会の多角的コミュニケーションの最初の姿が、具体的に見え始める契
機となった。右肩上がりの時代の「タテ型コミュニケーション」では、「上流」はも
とより「下流社会」でもコミュニケーションはとれない。コミュニケーションがとれ
ないところで、コミュニティー、仲間はつくれない。 戸田代表のあいさつでは、コミュニケーション能力の大切さが強調された。今回の総
選挙は、構造社会の多角的コミュニケーションの最初の姿が、具体的に見え始める契
機となった。右肩上がりの時代の「タテ型コミュニケーション」では、「上流」はも
とより「下流社会」でもコミュニケーションはとれない。コミュニケーションがとれ
ないところで、コミュニティー、仲間はつくれない。この後の来賓あいさつでは、多くの方からも代表の発言にふれて、こうしたコミュニ ケーション能力の重要性が述べられた。  またこれに関連して、都議選でマニフェストの枠で二十人の新人が誕生したことにつ
いては、手塚都連幹事長(当時)の尽力を外してはないこと。総選挙で手塚氏は惜敗
したが、都議選でこの結果を残したことが、民主党としても都連としても「次」への
重要な足がかりとなっていることにも触れた。 またこれに関連して、都議選でマニフェストの枠で二十人の新人が誕生したことにつ
いては、手塚都連幹事長(当時)の尽力を外してはないこと。総選挙で手塚氏は惜敗
したが、都議選でこの結果を残したことが、民主党としても都連としても「次」への
重要な足がかりとなっていることにも触れた。
 呉竹会会長の頭山興助氏からは、若い議員に対して「権力闘争を戦い抜いて政策を実
現する」ことの重要性やその主体性、闘争性について、深い識見に基づいた激励が
あった。頭山氏は、アジア近代の曙において孫文と深い交流・連帯を結んだ頭山満翁
の孫にあたり、戸田代表は懇意にさせていただいている。この日も呉竹会から多数、
ご参加いただいた。 呉竹会会長の頭山興助氏からは、若い議員に対して「権力闘争を戦い抜いて政策を実
現する」ことの重要性やその主体性、闘争性について、深い識見に基づいた激励が
あった。頭山氏は、アジア近代の曙において孫文と深い交流・連帯を結んだ頭山満翁
の孫にあたり、戸田代表は懇意にさせていただいている。この日も呉竹会から多数、
ご参加いただいた。
 乾杯のごあいさつは、広田一・参院議員、大塚耕平・参院議員、藤田幸久・前衆院議
員、五十嵐文彦・前衆院議員。代表して広田参院議員から乾杯のご発声。ほかにも蓮
舫・参院議員、高山智司・衆院議員、渡辺周・衆院議員、上野賢一郎・衆院議員にご
あいさついただいた。上野議員は今回初当選(自民党)で、以前から関西での囲む会
などに参加してきた同人会員でもある。「今はタイゾー君ばかりが注目されている
が、政策論争でタイゾー君を凌駕する活躍をする」と力強い抱負を述べた。 乾杯のごあいさつは、広田一・参院議員、大塚耕平・参院議員、藤田幸久・前衆院議
員、五十嵐文彦・前衆院議員。代表して広田参院議員から乾杯のご発声。ほかにも蓮
舫・参院議員、高山智司・衆院議員、渡辺周・衆院議員、上野賢一郎・衆院議員にご
あいさついただいた。上野議員は今回初当選(自民党)で、以前から関西での囲む会
などに参加してきた同人会員でもある。「今はタイゾー君ばかりが注目されている
が、政策論争でタイゾー君を凌駕する活躍をする」と力強い抱負を述べた。



 市町村議員も多数参加。〇七年は参院選とともに統一地方選が行われるが、ここで
「顔と政策が一致する」、マニフェスト感覚で地域の信頼関係を築ける地方議員をど
れだけつくれるかは、二大政党による政権交代の基盤を成熟させていくうえで、重要
なステップである。 市町村議員も多数参加。〇七年は参院選とともに統一地方選が行われるが、ここで
「顔と政策が一致する」、マニフェスト感覚で地域の信頼関係を築ける地方議員をど
れだけつくれるかは、二大政党による政権交代の基盤を成熟させていくうえで、重要
なステップである。読者会や囲む会を行っているグループとして、千葉と埼玉の会員があいさつ。千葉は 窪田・富里市議(同人)が、埼玉は白川・越谷市議(同人)が代表したスピーチ。ま た久喜市長選に挑戦した後上氏、越谷市長選に挑戦した島村氏(同人)からも、それ ぞれの総括が語られた。  金玉彩・韓国大使館参事官からは、韓国は歴史をカードにする意思はなく、一般の国
民がさまざまな歴史観をもつことは当然だと考えているが、一国を代表する首相や大
臣、政治家が戦後国際社会で確認されてきたことを覆すような言動をとることは看過
できないと述べられた。さらに韓国も台湾も政権交代をした、日本もそろそろ必要で
は? と日本の主権者を激励、会場からは共感の拍手があがった。 金玉彩・韓国大使館参事官からは、韓国は歴史をカードにする意思はなく、一般の国
民がさまざまな歴史観をもつことは当然だと考えているが、一国を代表する首相や大
臣、政治家が戦後国際社会で確認されてきたことを覆すような言動をとることは看過
できないと述べられた。さらに韓国も台湾も政権交代をした、日本もそろそろ必要で
は? と日本の主権者を激励、会場からは共感の拍手があがった。
 最後に、「バッジをつけない主権者」として地道に活動している会員とともに、古賀
副代表が中締めのあいさつ。乾杯後の短い時間を除いてずっと、あいさつが間断なく
続けられたが、壇上からのメッセージにあいづちをうちつつ、そこここで歓談の輪が
ひろがり、終始熱気につつまれた二時間余りであった。 最後に、「バッジをつけない主権者」として地道に活動している会員とともに、古賀
副代表が中締めのあいさつ。乾杯後の短い時間を除いてずっと、あいさつが間断なく
続けられたが、壇上からのメッセージにあいづちをうちつつ、そこここで歓談の輪が
ひろがり、終始熱気につつまれた二時間余りであった。上田埼玉県知事、木村和歌山県知事ほかより、お祝いのメッセージをいただい た。 時間の関係で、市町村議員のみなさんにはほとんどあいさつの時間がとれず、名前の 紹介だけになってしまったが、〇七年あるいはそれぞれの「次」をめざして、いっそ うの奮闘を期待したい。また「バッジをつけない主権者」の紹介、発言もきわめて限 定されてしまったが、政策で人間関係をつくる活動をともに担うフォロワ―の役割 は、ますます重要になるし、こうした「バッジをつけない主権者」活動のなかから選 抜され、信頼されてバッジをつけるということが、本来のあり方であろう。こうした ことを根付かせるためにも、「バッジをつけない主権者」の参加をさらに増やしてい くことが課題である。 (バッジをつけない主権者活動のエースともいえる「丸さん」はじめ、何人かを紹介 し損ねてしまいました。ゴメン!) | ||
| 「第7回 関西・戸田代表を囲む会」 | ||
 10月22日大阪市内で、第7回関西・戸田代表を囲む会を開催。 10月22日大阪市内で、第7回関西・戸田代表を囲む会を開催。
がんばろう、日本!国民協議会・同人 杉原卓治 | ||
| 「京都で「囲む会」を開催」 | ||
 10月3日、京都センチュリーホテルで第11回関西政経セミナーを、引き続き11日にはキャンパスプラザ京都で、第1回京都・戸田代表を囲む会を開催。いずれも、今年4月より毎月続けてきた「『日本再生』青年学生読者会」のメンバーが中心になって組織した。
「総選挙総括」をテーマにした第1回京都・戸田代表を囲む会には、総選挙ボランティアにかかわった学生を中心に30余名が参加。 10月3日、京都センチュリーホテルで第11回関西政経セミナーを、引き続き11日にはキャンパスプラザ京都で、第1回京都・戸田代表を囲む会を開催。いずれも、今年4月より毎月続けてきた「『日本再生』青年学生読者会」のメンバーが中心になって組織した。
「総選挙総括」をテーマにした第1回京都・戸田代表を囲む会には、総選挙ボランティアにかかわった学生を中心に30余名が参加。 はじめに戸田代表から「政権選択選挙の定着とは、有権者が『首相候補を選ぶ』『政権能力(政策実現力)を選ぶ』『主要な政策のインパクト』の相互関係で選択すること。問題設定と問題解決能力で流れを変えることが可能になった」と提起。
総選挙で前原誠司選対(京都2区)の副事務長をつとめた、隠塚(おんづか)功・京都市議は「2区は前原対山本ではなく、前原対小泉であった。主要な政策では政権を担える政党の能力が問われた。政権選択選挙が定着した選挙であった」と選挙戦を総括。 はじめに戸田代表から「政権選択選挙の定着とは、有権者が『首相候補を選ぶ』『政権能力(政策実現力)を選ぶ』『主要な政策のインパクト』の相互関係で選択すること。問題設定と問題解決能力で流れを変えることが可能になった」と提起。
総選挙で前原誠司選対(京都2区)の副事務長をつとめた、隠塚(おんづか)功・京都市議は「2区は前原対山本ではなく、前原対小泉であった。主要な政策では政権を担える政党の能力が問われた。政権選択選挙が定着した選挙であった」と選挙戦を総括。
 続いて民主党選対本部事務局次長をつとめた福山哲郎・参議院議員は、「小選挙区制が日本に確実に定着した選挙」と総括したあと、7月以降の政治攻防戦のダイナミズムを事実に即して整理。 続いて民主党選対本部事務局次長をつとめた福山哲郎・参議院議員は、「小選挙区制が日本に確実に定着した選挙」と総括したあと、7月以降の政治攻防戦のダイナミズムを事実に即して整理。「8月27日からの三日間は、民主党、自民党とも相当ぎりぎりのところまできていた」など、政党政治の新たなステージの中で感じたことが率直に語られ、「マニフェストをどのように国民に届けるか。今回小泉自民党がターゲットにした層をマーケティングすることが緊要」と課題が提示された。 (左から・戸田代表、福山参院議員、隠塚京都市議) ふたたび戸田代表から「『下流層』にも日本再生にかかわってもらうよう、どうアプローチするか。『上流層』には組織者・伝達者の責務が問われる。これが分権社会、コミュニティーの再生。決定的には人間力とメッセージ力であり、社会と向き合うエネルギーでは、三十代、二十代、十代に力点がすでに移っている」と提起があった。 来る10月22日には大阪で、第7回関西・戸田代表を囲む会を、尾立源幸・参議院議員をゲストスピーカーに迎え開催。堺市長選(10月2日)の総括を含め、政策=政権選択選挙の定着の中での政党政治や首長候補のありかた(課題)について議論を深める。 がんばろう、日本!国民協議会・同人 杉原卓治 | ||
| 「第11回 関西政経セミナーin京都」 | ||||||||||||||
 10月3日、第11回関西政経セミナーを初めて、京都にて開催。 10月3日、第11回関西政経セミナーを初めて、京都にて開催。 講師は慶應大学の添谷芳秀先生。この間の京都での「日本再生」読者会の蓄積を基礎に、学生を中心に約80名が参加。
事前に学生が、添谷先生の「日本の『ミドルパワー』外交」の学習会を行っていたということで、添谷先生から、最初に質問を受けてから講演をしましょうとの提案。その場ですぐに、質問者を決めて準備した。
講演後には簡単な懇親会を開催。木村・大阪市議(同人)をはじめ、それぞれから総選挙などでの活動報告が行われた。 講師は慶應大学の添谷芳秀先生。この間の京都での「日本再生」読者会の蓄積を基礎に、学生を中心に約80名が参加。
事前に学生が、添谷先生の「日本の『ミドルパワー』外交」の学習会を行っていたということで、添谷先生から、最初に質問を受けてから講演をしましょうとの提案。その場ですぐに、質問者を決めて準備した。
講演後には簡単な懇親会を開催。木村・大阪市議(同人)をはじめ、それぞれから総選挙などでの活動報告が行われた。 | ||||||||||||||
| 「江田同人、議員活動20周年を祝う」 | ||||||||||||||
  10月2日、江田健治・同人の「議員活動・無料法律相談会20周年」を祝う集まりが開催された。 10月2日、江田健治・同人の「議員活動・無料法律相談会20周年」を祝う集まりが開催された。江田さんは白井町議・市議、六期20年で昨年からは議会議長も務める。この間続けてきた無料法律相談会も20周年を迎え、白井市長はじめ周辺自治体の首長、法律相談のパートナーである法理事務所などの呼びかけで、この日の祝賀会となった。 前半では、「地方分権と市民主権 創造!北総の未来を私たちの手で」と題してパネルディスカッション。中村・白井市議、松本・印西市議、岩田・白井市議に長門同人というメンバーで、時間不足ながらも「地方議会議員」の役割について議論。(写真 右上)   続く祝賀会では、発起人となった白井市長はじめ周辺自治体の首長、議会議長、議員などが次々と紹介され、江田さんの幅広い活動とその蓄積が改めて披露された。 続く祝賀会では、発起人となった白井市長はじめ周辺自治体の首長、議会議長、議員などが次々と紹介され、江田さんの幅広い活動とその蓄積が改めて披露された。戸田代表も、「来賓」として壇上に。(左から根本・野田市長、若井・前議員、構想日本・冨永氏、戸田代表) | ||||||||||||||
| 「前原新代表、街頭デビュー」 | ||||||||||||||
 9月30日夕刻、サラリーマンの町新橋で、民主党・前原新代表の街頭デビューとなる街頭宣伝活動が行われた。前原代表が演説するとあって、駅前広場には多くの人だかり。笠ひろふみ議員の司会で、柚木道義議員(アノ橋本元総理の子息を小選挙区で破った!)、蓮舫参院議員などが次々と訴える。前原代表は予算委員会後にかけつけることになっていたが、あいにく月末の金曜日ということで、渋滞に巻き込まれ、到着がかなり遅れたため、待ちきれずにその場を離れてしまった人もかなりいたのは、残念。
前原代表が到着すると、一気にその場の注目度が高まる。予算委員会での質疑などを紹介しながら、この一年の任期に、政治人生の全てをかける決意で、国民の期待に答えていくためにかんばると力強く訴えた。
前原代表への注目が高いこの時期に、積極的に露出して「民主党の再出発」をアピールすることと、10月の参院神奈川補選で、流れを変える足がかりをつくることはきわめて重要だ。 9月30日夕刻、サラリーマンの町新橋で、民主党・前原新代表の街頭デビューとなる街頭宣伝活動が行われた。前原代表が演説するとあって、駅前広場には多くの人だかり。笠ひろふみ議員の司会で、柚木道義議員(アノ橋本元総理の子息を小選挙区で破った!)、蓮舫参院議員などが次々と訴える。前原代表は予算委員会後にかけつけることになっていたが、あいにく月末の金曜日ということで、渋滞に巻き込まれ、到着がかなり遅れたため、待ちきれずにその場を離れてしまった人もかなりいたのは、残念。
前原代表が到着すると、一気にその場の注目度が高まる。予算委員会での質疑などを紹介しながら、この一年の任期に、政治人生の全てをかける決意で、国民の期待に答えていくためにかんばると力強く訴えた。
前原代表への注目が高いこの時期に、積極的に露出して「民主党の再出発」をアピールすることと、10月の参院神奈川補選で、流れを変える足がかりをつくることはきわめて重要だ。(参院神奈川補選は10月23日投票。自民党は川口順子・元外相を擁立。民主党は公募で牧山ひろえ氏を公認。) | ||||||||||||||
| 「北神けいろう君を励ます会」 | ||||||||||||||
  8月24日 京都4区から立候補予定の北神けいろう君を励ます会を開催。
「日本再生」学習会を続けている学生を始め、50名ほどが参加。
政権交代にむけて小選挙区での必勝を誓った。 8月24日 京都4区から立候補予定の北神けいろう君を励ます会を開催。
「日本再生」学習会を続けている学生を始め、50名ほどが参加。
政権交代にむけて小選挙区での必勝を誓った。 | ||||||||||||||
| 「松沢知事」 | ||||||||||||||
 8月22日。神奈川県庁にて、松沢知事にインタビュー(9/1号に掲載)。 8月22日。神奈川県庁にて、松沢知事にインタビュー(9/1号に掲載)。知事就任から二年。県議会とのあつれきは今も続いているがマニフェストに基づいた総合計画を作成し、ようやく、マニフェスト実行の体制に移りつつある。 また検証についても、第三者的な検証委員会、自己評価、総合計画の進捗についての白書としっかり行われている。マニフェストは言いっぱなしではダメで、実現に責任を持たなければならないこと、そのためには毎年、進捗状況を公開しなければならないこと、そういう重い責任を負うのだと、強調された。 検証がしっかり行われることで、マニフェストサイクルはさらに前へ一歩進むことになる。 | ||||||||||||||
| 「第9回埼玉・戸田代表を囲む会」 | ||||||||||||||
 第9回埼玉・戸田代表を囲む会が、7月29日越谷市の中央市民会館で「ローカルマニフェストで、かく戦えり」をテーマに開催され、地方議員や市民など約25名が参加した。 第9回埼玉・戸田代表を囲む会が、7月29日越谷市の中央市民会館で「ローカルマニフェストで、かく戦えり」をテーマに開催され、地方議員や市民など約25名が参加した。ゲストスピーカーには、7月24日の投票からの疲れを見せずに二期目の当選を果した木下博信・草加市長と、同じく3日投票で二期目を勝ち取った花輪智史・民主党都議会議員の二人が講演した。 松沢神奈川県知事を始めとして4年前から始まったローカルマニフュスト運動の推進者である木下市長からは、埼玉における社会的検証に耐えうる典型的シティマネージャーとしての型が実感された。それは決定は主権者が行ない、役所は決まったことを合理的に執行する、市長は合理判断で税金の集め方、使い方を情に流されず執行するというものである。 また地方選挙では初めて民主党として提起した「東京マニフェスト」を選挙活動の中心軸に置き、政党の規律化や市民への伝達、合意形成というマネージメント能力をいかに発揮したのか、花輪都議から問題提起を受けた。 それぞれローカルマニフェストを街頭演説や集会で、情感を込めて訴えたことに、市民は反応を示しており(木下市長は今回は街頭演説を積極的にこなた。市議時代から4回の選挙を経験したが、熱心に耳を傾ける市民や始めて拍手を受けた)、低投票率が予想されていたにもかかわらず都議会選挙も草加市長選挙も前回より底上げされている。一昨年の衆議院選挙(マニフェスト選挙)から首長選挙や地方議員選挙でも政党・政策本位の選挙戦への転換が始まっている。 8月の久喜市長選挙に立候補予定の後上民子(ごがみ・たみこ)前久喜市議が開会あいさつ。花輪都議からは「東京マニフェスト」作成の過程と責任者に触れ、「業界や団体や特定地域の代表としての地方議員やその支援組織の要求をそのまま受けとってしまってはマニフュエストは作成できない。一切の既得権に妥協せず、枠組みができるまでは少数者で決定する必要がある」と報告した。また石原都政への業績評価の視点から、「石原知事は政官業への切り込みが弱く、浜渦元副知事を東京都の外郭団体へ天下りさせたことに典型的に示されるように、旧来の枠組みの延長でしかない」と強調した。  木下市長は一期目の実績と二期目の課題に触れ、「目標は変わっておらず、市役所を変えること、つまり市民が発想、役所が実行をするという(役所の都合ではなく、市民の目で見ていく)ことを基本原則としている」として具体的取り組みを紹介した。①これまでの市役所によくあった所謂「たらい回し」を無くすため、総合窓口を設置した。②日曜日や夜間開庁を実現し、職員には時間差勤務を導入し、人件費の増加を抑制している。③特区申請でコンビニでも納税ができるようにしたなど。しかも前任者から引き継いだ財政状況も借金を増やさず、貯金を減らさない結果となっていることが話された。 木下市長は一期目の実績と二期目の課題に触れ、「目標は変わっておらず、市役所を変えること、つまり市民が発想、役所が実行をするという(役所の都合ではなく、市民の目で見ていく)ことを基本原則としている」として具体的取り組みを紹介した。①これまでの市役所によくあった所謂「たらい回し」を無くすため、総合窓口を設置した。②日曜日や夜間開庁を実現し、職員には時間差勤務を導入し、人件費の増加を抑制している。③特区申請でコンビニでも納税ができるようにしたなど。しかも前任者から引き継いだ財政状況も借金を増やさず、貯金を減らさない結果となっていることが話された。また議会と市長の関係では、「市役所と市民の距離が縮まれば縮まるほど、野党的立場の議員からは政策提言ではなく、執行権に介入する質問(人事など)に変化している」と話し、「予算・決算委員会の議論は、予算が増えたか減ったかではなく、事業の成果が上がったのかのかどうかという『事業審査』であるべき、その意味では市長は執行権に最大の責任を追うべきである」と強調した。  戸田代表からは、木下市長のスタイル(立法と執行の分立)がいわゆるシティー・マネージャーの型であるとしたうえで、地方自治のありかたについては、現在のような大統領制(議会との二元代表制)やシティ・マネージャー制あるいは議員の互選制など、いろいろな仕組みがあるが、どのようなシステムを取るのかということも、住民が主権者として選択すべきものであるとのコメントがあった。 戸田代表からは、木下市長のスタイル(立法と執行の分立)がいわゆるシティー・マネージャーの型であるとしたうえで、地方自治のありかたについては、現在のような大統領制(議会との二元代表制)やシティ・マネージャー制あるいは議員の互選制など、いろいろな仕組みがあるが、どのようなシステムを取るのかということも、住民が主権者として選択すべきものであるとのコメントがあった。また行政の肥大化が指摘されているが、それは立法が機能していないことを意味しており、(決定の主体たる)主権者が不在ということになる。ローカル・マニフェストを推進するということは、立法・議会を機能させながら、行政権が社会的な検証を受けるということである。またフォロワーとしてリーダーを見るときに、経営能力があるかどうか(自分自身にそれがなくても)などガバナンス能力があるかどうかから検証していくことが求められると、集約した。 最後に、田口初江吉川市議の閉会あいさつで終了した。 | ||||||||||||||
| 「'05都議選・祝勝&ご苦労さま会開催」 | ||||||||||||||
 7月21日、「がんばろう、日本!」国民協議会事務所にて、都議選の祝勝&ご苦労さま会を開催、見事当選を果たした都議をはじめとして、選挙戦をともに戦った会員や仲間約百名が参加した。 7月21日、「がんばろう、日本!」国民協議会事務所にて、都議選の祝勝&ご苦労さま会を開催、見事当選を果たした都議をはじめとして、選挙戦をともに戦った会員や仲間約百名が参加した。冒頭、戸田代表より都議選の総括ポイントが提起された。低投票率が予想されるなか、過去最低ライン(前々回の40%)を4ポイント引き上げたのは、マニフェストの政治文化に反応できる層、言い換えれば、国政選挙では民主党に投票するが、地方選挙では投票に行かないという層の一部が、今回は投票に行ったこと。それが可能だったのは「東京マニフェスト」(地方議会選挙ではじめて、会派としてマニフェストを提示したこと)であり、それを体現できる候補者と活動によるものである。  「投票率がもう少し高ければ…」というのではなく、有権者の自覚に訴え、覚醒させるまでの力を持った候補者を発掘し、育成し、擁立することが、今後のさらなる前進にとっては決定的であり、またそういう候補者や選対をつくりあげていく活動に、会員各位はさらに主体的に関わり「次」を準備しようとの提起があった。 「投票率がもう少し高ければ…」というのではなく、有権者の自覚に訴え、覚醒させるまでの力を持った候補者を発掘し、育成し、擁立することが、今後のさらなる前進にとっては決定的であり、またそういう候補者や選対をつくりあげていく活動に、会員各位はさらに主体的に関わり「次」を準備しようとの提起があった。続いて同人でもある花輪都議が乾杯のあいさつ。第二党となった都議会民主党を、マニフェストによって紀律化されたものとする決意が述べられた。続いて次々と都議があいさつ。躍進はしたが、自公の得票にはまだ及ばない、政権交代を果たすためには、政策観があることはもちろん、はつらつとしたエネルギー溢れる候補者をさらに数多く、地域から擁立していかなければならないとの旨が、それぞれから語られた。  そうした若いエネルギーのひとつの焦点が、十一月に予定されている葛飾区長・区議選挙である。区長選に挑戦予定の鈴木烈・葛飾区議(32歳。同人/写真左下)は、仲間の都議からも熱いエールを受けながら、力強く抱負と決意を述べた。 そうした若いエネルギーのひとつの焦点が、十一月に予定されている葛飾区長・区議選挙である。区長選に挑戦予定の鈴木烈・葛飾区議(32歳。同人/写真左下)は、仲間の都議からも熱いエールを受けながら、力強く抱負と決意を述べた。 都議選をともに戦った同人、会員の市議・区議、他県の地方議員、これから首長選へ挑戦する同人など、各地の会員からも次期総選挙ならびに07年統一地方選へのロードマップを念頭に、選挙という戦場そのものを変えていく活動の総括や今後の取り組みが述べられた。 都議選をともに戦った同人、会員の市議・区議、他県の地方議員、これから首長選へ挑戦する同人など、各地の会員からも次期総選挙ならびに07年統一地方選へのロードマップを念頭に、選挙という戦場そのものを変えていく活動の総括や今後の取り組みが述べられた。あいさつした都議は、初鹿明博、柿沢未途、伊藤正樹、伊藤悠、野上幸絵、猪爪まさみ、吉田康一郎、、酒井大史、原田大、小澤昌也の各氏(順不同・敬称略)。健闘した滝口学さん(荒川区)からは、捲土重来を期してがんばるとの、元気な決意が述べられた。 | ||||||||||||||
| 「政治インフラとしての住民自治を―京都・青年学生読者会が自治体議員フォーラムを開催」 | ||||||||||||||
 7月12日、キャンパスプラザ京都で、「今なぜ、ローカルマニフェストか?―若手
市議大いに語る」を開催。学生を中心に33名が参加した。 7月12日、キャンパスプラザ京都で、「今なぜ、ローカルマニフェストか?―若手
市議大いに語る」を開催。学生を中心に33名が参加した。計画・準備したのは、今年4月から毎月『日本再生』読者会を開催してきた、京都青年学生読者会。権力構造の最末端で国民主権の最前線でもある地域で活動する、同人議員の木村正治・東大阪市議、佐野英史・奈良三郷町議(いずれも民主党)、民主党京都の青年局長でもある、隠塚(おんづか)功・京都市議、南部としこ・京田辺市議(民主党)が参加。「有権者との関係をどのように変えてきたか」「ローカルマニフェストをいかに活用していくか」の二つの論点で討議に入った。  まず、各議員から自己紹介を兼ね「なぜ議員になったのか」が語られた。共通するのは、民主主義の政治文化をつくるために、議員という人的インフラを自ら買ってでたこと(人的インフラを探し育てるのは主権者の義務)。有権者との関係では、徹底した情報公開(説明責任)。情報の共有なくして、マニフェスト・サイクル(実施=検証=再実施)はできず、主権者として自立を促すことが決定的。ローカル・マニフェストを活用するためには、首長・議員の説明能力と、住民の検証能力を相互に高めあうことが不可欠である。民主党京都府連では「京都マニフェスト」を準備し、知事に政策要求を行っていくと報告があった。 まず、各議員から自己紹介を兼ね「なぜ議員になったのか」が語られた。共通するのは、民主主義の政治文化をつくるために、議員という人的インフラを自ら買ってでたこと(人的インフラを探し育てるのは主権者の義務)。有権者との関係では、徹底した情報公開(説明責任)。情報の共有なくして、マニフェスト・サイクル(実施=検証=再実施)はできず、主権者として自立を促すことが決定的。ローカル・マニフェストを活用するためには、首長・議員の説明能力と、住民の検証能力を相互に高めあうことが不可欠である。民主党京都府連では「京都マニフェスト」を準備し、知事に政策要求を行っていくと報告があった。地域の権力構造=意志決定のあり方を変える四者四様の組織戦の型が語られ、今後の協奏競合関係の入り口がつくられた。10月3日の関西政経セミナー(京都)と10月11日の第一回京都「戸田代表を囲む会」の組織課題が明らかになった。 懇親会にも20名が参加し、夜遅くまで熱い議論が行われた。 次回読者会は8月5日、キャンパスプラザ京都にて。 同人・杉原卓治 | ||||||||||||||
| 「大阪で囲む会―マニフェストの根付きとガバナンスの集」 | ||||||||||||||
 7月9日、大阪で福山哲郎参議院議員と尾立源幸参議院議員をゲストに、第6回関西「戸田代表を囲む会を開催。36名が参加し、マニフェスト政治文化の定着と政党のガバナンス能力の集積について議論を深めた。 7月9日、大阪で福山哲郎参議院議員と尾立源幸参議院議員をゲストに、第6回関西「戸田代表を囲む会を開催。36名が参加し、マニフェスト政治文化の定着と政党のガバナンス能力の集積について議論を深めた。まず、福山哲郎参議院議員から「マニフェストについて、有権者にある種の根付きができてきている。問われているのは、民主党に政権を任せていこうというまでの、政策をはじめとする魅力だ」と、この間の政治攻防戦を総括。特に二大政党制の政治インフラとして情報ギャップをどう埋めていくか、有権者とのとコミュニケーション強化が課題であり、政権戦略としてはどの時期に選挙を想定するかでマニフェストの優先順位や訴え方が変わってくる、と提起された。  尾立参議院議員から郵政民営化をめぐる論点整理があったあと、戸田代表から「主権在民を前提にした政治制度では、ガバナンス能力が集積するものと、破産するものに分解する」とコメントがあり討議に入った。 尾立参議院議員から郵政民営化をめぐる論点整理があったあと、戸田代表から「主権在民を前提にした政治制度では、ガバナンス能力が集積するものと、破産するものに分解する」とコメントがあり討議に入った。木村正治・東大阪市議、畠中光成・民主党兵庫9区、熊田篤・同大阪1区、長尾敬・同14区各総支部長から「地域の権力構造をどのように変えてきたか」各々報告。戸田代表から「衆議院解散権はいい意味の『国民の常識』で縛られている。  野党第一党が政権交代の戦略からどのシナリオで解散に持ち込んでいくかというのも初めて。ローカルマニフェストをめぐる分解を含め、政策市場の空間が大量に派生している」とまとめがあった。 野党第一党が政権交代の戦略からどのシナリオで解散に持ち込んでいくかというのも初めて。ローカルマニフェストをめぐる分解を含め、政策市場の空間が大量に派生している」とまとめがあった。第四回大会の課題はより鮮明になった。がんばろう、日本!国民協議会の全国展開を速やかに進めよう。 同人・杉原卓治 | ||||||||||||||
| 「第一回 埼玉・政経セミナー」 | ||||||||||||||
 5月29日第1回埼玉・政経セミナーが、越谷市民会館で開催され、県内の地方議員を含め市民約150人が参加した。主催は「がんばろう、日本!」国民協議会・埼玉。 5月29日第1回埼玉・政経セミナーが、越谷市民会館で開催され、県内の地方議員を含め市民約150人が参加した。主催は「がんばろう、日本!」国民協議会・埼玉。「ローカルマニフェストが切り開く地域ガバナンス―今住民が力を発揮する時―」をテーマに、自治体のトップとしての齋藤健埼玉県副知事(上田清司知事代理)、政権準備党・政党のリーダーとしての枝野幸男民主党衆議院議員、政策市場を切り開いてきたNPO代表としての加藤秀樹「構想日本」代表の3人をパネラーに、石津美知子「がんばろう、日本!」国民協議会事務局長の司会で3時間に及ぶパネルデスカッションが展開された。 最初にマニフェストで政治・行政がどのような段階に入ったのかについて話された。枝野氏は「二大政党制が進む中で、万人にとって得になるという政策はありえない。むしろこれからはマイナスをどのようにシェアするか、これを選挙の時に有権視野と確認しないとやれない。そのためには事前の党内論議で意思統一することが重要」。加藤氏は「マニフェストが単に公約をカタカナに変えただけという風潮には注意しなければならないが、同じ政策集で全候補者が統一されたことは評価できる」。齋藤氏は「マニフェストによって選挙制度、意志決定、統治機構、官と民のあり方をどうするのかなど課題は大きくなっている」と発言。  続いて、地方分権とは単に国と地方の権限・財源の奪い合いではなく、地方の自立と自治であり、ローカルマニフェストはそのための「気付きの道具」であるという観点から論議が進められた。 続いて、地方分権とは単に国と地方の権限・財源の奪い合いではなく、地方の自立と自治であり、ローカルマニフェストはそのための「気付きの道具」であるという観点から論議が進められた。加藤氏は構想日本がコーディネートしてきた全国12自治体での「事業仕分け作業」に触れ、そもそも公共とは何かということから議論してみると、全体事業の大体30%近くの事業は当該自治体の守備範囲ではない、という結論に達する。このような仕分け通りの運用ができないのは、国の基準やルールに地方が縛られていることが原因」と指摘。 これに応えて齋藤氏は、昨年9月に上田知事は独自に事業仕分けを実施し、約40%が県担当ではないとしたが「それでは道路予算を福祉予算に振り向けるのかといえば、現状ではこれができない(補助金は使用目的が限定されている)。そこで限られた予算をどうしていくのか、これがマニフェストである」。枝野氏は「マニフェストを掲げて当選すれば、市民の支持であり、誰にも文句を言われず(議論なしで)政策を推し進める正統性をもつことになる」と発言。 また、分権を進めていくうえでは自治体のマネージメント能力、運営能力が問われている、このなかで市長や議員を選んだ有権者には選んだ責任があり、地方議会・議員に何が問われているのかという点で、論議は進んだ。 齋藤氏は「今後は(限られた資源の配分をめぐって)自治体と住民の軋轢が高まり、政策を示せないトップは淘汰されていく、またそういう自治体からは住民の流出が起こるかもしれない。またマニフェストは常に検証され続けることで首長のリーダーシップが問われ、議会が政策論争で活性化されていく」と指摘。  枝野氏は「自治体はこれまではどんなに財政がひどくなっても、結局は国が面倒を見てきた。しかし人口減少時代に入りそれができない。だから地方政治の水準をあげなければならない。二元代表制である地方議会で与党、野党というのは意味がない。議員は首長のマニフェストへの賛否を、項目でいいので明らかにすべき」と発言。さらに憲法論議にも触れ「これまで司法、立法、行政というわけ方をしてきたが、行政での内閣や首長は執政権を有しており、単に法を行うだけでなく政治判断を含む執行権を行使している。官僚はこれとは違い政治的中立性を保つ『行法』という位置づけが必要。」 枝野氏は「自治体はこれまではどんなに財政がひどくなっても、結局は国が面倒を見てきた。しかし人口減少時代に入りそれができない。だから地方政治の水準をあげなければならない。二元代表制である地方議会で与党、野党というのは意味がない。議員は首長のマニフェストへの賛否を、項目でいいので明らかにすべき」と発言。さらに憲法論議にも触れ「これまで司法、立法、行政というわけ方をしてきたが、行政での内閣や首長は執政権を有しており、単に法を行うだけでなく政治判断を含む執行権を行使している。官僚はこれとは違い政治的中立性を保つ『行法』という位置づけが必要。」加藤氏は「そもそも地方自治体の仕組みをどうするのか、二元代表制ではチェック・アンド・バランスが問われており、議会の立法機能を行使するようもともとのスタートラインに立つべき」と指摘した。 今回のセミナーには国民主権の底上げ、民主主義のインフラ整備にむけ、それぞれの分野で活躍しているトップリーダーがパネラーとして発言したが、フロアにはバッチをつけた主権者(地方議員約20名や市長・市長予定候補者)とバッチをつけない主権者(市民)が参加し、会場そのものが構造社会の小さきモデルとなっている。地元記者は「今日はどういうふうに人が集まるのか、まったく見当がつかない」と言っていたが、まさに同質性・同類性による同心円的拡大(だれそれの「系列」で何人というような「足し算」)では、「がんばろう」の活動は見えない。 「国民主権の底上げ」「政治文化を変える」という基盤整備の活動を徹底的に行うこと、そのうねりによって、新しい時代の価値観・方向性から既存の組織・人間関係を巻き込み、再編していくことこそが、「がんばろう」の活動である。だからこそ既存の組織関係、俗に言う「しがらみ」を超えて、新しい時代の価値観・方向性からストレートに議論を回し、個々の総和をはるかに超えた相乗的な連鎖でエネルギーを発揮する場となる。 壇上はもとより、フロアの参加者も「濃い」内容に、「はじめは三時間は長いと思ったが、あっという間だった」「他では聞けないような内容で、おもしろかった」との感想。パネラーも異口同音に「これだけの内容を、みなさん熱心に聞いていた」と感心することしきりであった。 | ||||||||||||||
| 「第10回関西政経セミナーを開催」 | ||||||||||||||
 4月24日大阪市内で、第10回関西政経セミナーを開催(参加100名)。
はじめに、村田晃嗣・同志社大学教授より、今後の国際関係を考える視点として「米外交を考える際に、『ひとつに結束したアメリカ』は国際社会にいい影響を与えるだろうか」と問いかけがあった。つまり「分裂したアメリカ」ととらえるのか、「アメリカは選択肢が準備された世界」ととらえるのかでは、問題設定が180度違ってくる。また、「2015年問題(国連安保理改革のリミット)を控えて、長期的視野で国連改革を考えることが重要」と30年代の日本の歴史教訓を引きながら「(安保理入りを果たせなかった場合の)失望のマネジメント」までのガバナンスの必要性が強調された。 4月24日大阪市内で、第10回関西政経セミナーを開催(参加100名)。
はじめに、村田晃嗣・同志社大学教授より、今後の国際関係を考える視点として「米外交を考える際に、『ひとつに結束したアメリカ』は国際社会にいい影響を与えるだろうか」と問いかけがあった。つまり「分裂したアメリカ」ととらえるのか、「アメリカは選択肢が準備された世界」ととらえるのかでは、問題設定が180度違ってくる。また、「2015年問題(国連安保理改革のリミット)を控えて、長期的視野で国連改革を考えることが重要」と30年代の日本の歴史教訓を引きながら「(安保理入りを果たせなかった場合の)失望のマネジメント」までのガバナンスの必要性が強調された。
 第二部に入り、木村良樹・和歌山県知事から「新しい時代に入った中で、自治の仕組みと国民意識、国と地方の責任をつきつめて考えていくべきだ」との問題提起をうけ、パネルディスカッションに入った。樽床伸二・衆議院議員(民主党地方主権調査会会長)は「右肩上がりの時代が終わり、経済・外交両面からも地方分権は不可欠」と持論を展開。木村知事は、三位一体改革が「カネの分配」にいかに換骨奪胎されていったかの事実経過を披瀝。また、「国体」を例にあげ、右肩上がりの時代の「フルセット主義」の継承か、住民主権による財政規律回復かを問うた。この3月に就任したばかりの岡本泰明・柏原市長は、「ローカルマニフェストは、奇をてらうものではない。改革の精神と理念を一致させるよう、職員の人事改革から取り組んでいる。市民の目は厳しい」と報告。マニフェストの実践はリーダー観までを変える。森山浩行・大阪府議、吉本誠兵庫県議から質問をうけ、ローカルマニフェストの検証について「情報公開を約束している」(岡本市長)「検証は選挙で。議会運営の改革が必要」(樽床議員)「議会の存在意義そのものが問われる」(木村知事)などと議論があった。 第二部に入り、木村良樹・和歌山県知事から「新しい時代に入った中で、自治の仕組みと国民意識、国と地方の責任をつきつめて考えていくべきだ」との問題提起をうけ、パネルディスカッションに入った。樽床伸二・衆議院議員(民主党地方主権調査会会長)は「右肩上がりの時代が終わり、経済・外交両面からも地方分権は不可欠」と持論を展開。木村知事は、三位一体改革が「カネの分配」にいかに換骨奪胎されていったかの事実経過を披瀝。また、「国体」を例にあげ、右肩上がりの時代の「フルセット主義」の継承か、住民主権による財政規律回復かを問うた。この3月に就任したばかりの岡本泰明・柏原市長は、「ローカルマニフェストは、奇をてらうものではない。改革の精神と理念を一致させるよう、職員の人事改革から取り組んでいる。市民の目は厳しい」と報告。マニフェストの実践はリーダー観までを変える。森山浩行・大阪府議、吉本誠兵庫県議から質問をうけ、ローカルマニフェストの検証について「情報公開を約束している」(岡本市長)「検証は選挙で。議会運営の改革が必要」(樽床議員)「議会の存在意義そのものが問われる」(木村知事)などと議論があった。
 最後に、戸田代表より「『回答を求める』講演会への参加から、『選択のための考え方を求める』参加・学習への転換で、ふつうの有権者も選択・責任・連帯の考える仲間作りをせよ」と示唆があった。行動提起として、第四回全国大会(10月23日東京砂防会館)までに、「ローカルマニフェスト推進・関西自治体議員フォーラム」(仮称)を立ち上げ、住民主権の道具としてのローカルマニフェスト定着の推進部隊としていきたい。 最後に、戸田代表より「『回答を求める』講演会への参加から、『選択のための考え方を求める』参加・学習への転換で、ふつうの有権者も選択・責任・連帯の考える仲間作りをせよ」と示唆があった。行動提起として、第四回全国大会(10月23日東京砂防会館)までに、「ローカルマニフェスト推進・関西自治体議員フォーラム」(仮称)を立ち上げ、住民主権の道具としてのローカルマニフェスト定着の推進部隊としていきたい。
同人・杉原卓治 | ||||||||||||||
| 「第8回 埼玉・囲む会」 | ||||||||||||||
 第8回埼玉・戸田代表を囲む会は、4月4日さいたま市のウイズユーを会場に「自治体再生の展望と政権戦略」をテーマに開催された。 第8回埼玉・戸田代表を囲む会は、4月4日さいたま市のウイズユーを会場に「自治体再生の展望と政権戦略」をテーマに開催された。ゲストスピーカーは、民主党政権戦略委員会事務局長であり、この三月に埼玉県連代表に就任した枝野幸男衆院議員。会場には埼玉県内の地方議員や市民など約30名が参加した。 今回の囲む会は参加対象者を地方議員中心としたが、それは政権交代の基盤整備を押しすすめるためには選択―責任―連帯の自治主体をどのようにつくりだすのか決定的であり、その問題設定と解決能力を競い合うリーダーとしての地方議員の役割が重要であるからに他ならない。このため民主党系の議員は勿論のこと、所謂保守系無所属議員も多数参加した。 枝野議員は、そもそも地方分権とは何かから話をはじめ、「明治維新以来日本は欧米に追いつき追い越せの目標を目指して、規格大量生産でやってきた。このモデルを進めるうえでは中央集権制が極めて有効であった。しかしこの目標を達成した今問われている価値は多様性ある社会である。これは分権でなければできない」と時代的背景から説明した。また「地方分権をすすめることは中央政府から権力を奪いとる権力闘争である。また憲法には自治体の権力規定がないのだから政権交代によって分権をすすめるしかない」と憲法改正と関連して提起された。さらに「全国一律の取り組みでは高齢者にも若者にも多様性を前提としたきめ細かさは実現できない。また地域がそれぞれの持ち味を発揮するシステムは蓄積されていない」と話した。最後に「地方分権の推進も政権交代も時間の問題であり、時代の要請であるが残された時間があまりないのも事実である」と締めくくった。 参加者からは「政権交代は必要であり、民主党の外交・安全保障政策も支持するが党内がバラバラに見える」「政権交代の時期とその体制をどうつくるのか」「ローカル政党の役割とは何か、中央政党との関係は」「首長選挙で民主党と自民党との相乗りが見受けられるが何故か」「ローカルマニフェストと地方議会の関係は」など多岐に及んだ。  講演と討議のなかでさまざまな切り口から繰り返し問われていたのは、「分権の本質がどこまで分かっているか」ということであった。分権とは脱中央主権であるが、それはとりもなおさず、住民自身が自らの責任で決定に参加し、その結果責任までを負う、ということにほかならない。だからこそ、ローカルマニフェストが必要になる、ということである。 講演と討議のなかでさまざまな切り口から繰り返し問われていたのは、「分権の本質がどこまで分かっているか」ということであった。分権とは脱中央主権であるが、それはとりもなおさず、住民自身が自らの責任で決定に参加し、その結果責任までを負う、ということにほかならない。だからこそ、ローカルマニフェストが必要になる、ということである。道州制や(お仕着せの)合併という「分権」論には、こうした住民自治の本質が抜けている。ここで「そもそも分権とはなにか」が問われていた(問われている)。 代表からは「今問われている問題は、分権という権力の分立でないと問題解決は出来ない。分権により住民の自治能力が生まれ、選択・責任・連帯という人間関係が作られる。現状分析から問題設定し、問題解決を3年で考える場合と、10年・15年で考える場合とでは解決方法が違ってくる。戦後の護送船団社会では同質性や類似性からの人間関係しか作れていなかったが、今は志向性、方向性から古い人間関係を作り変えていく能力=コミュニケーション能力が問われている。また有権者にも、主権者としての一部署に就くために必要な基礎学習と共に、それにふさわしい就労教育までを行う必要 がある。」と強調した。 最後に5月29日の枝野議員もパネラーとして参加する第1回埼玉・政経セミナー開催への協力を全体で確認した。 | ||||||||||||||
| 「市ヶ谷事務所にて二次会」 | ||||||||||||||
 第64回定例講演会は、民主党の政権戦略委員会の実務責任者である事務局長の枝野幸男衆院議員を講師に開催。 第64回定例講演会は、民主党の政権戦略委員会の実務責任者である事務局長の枝野幸男衆院議員を講師に開催。政権交代とはすなわち、総選挙で過半数をとることにつきる。そのために何をすべきなのか。枝野議員はそのための「有権者市場」の分析やターゲティングの絞込みなどについて、きわめて現実主義的かつ合理的な観点でお話をされた。 あいにく基礎自治体の議会はちょうど、予算審議の山場の時期ということで、「ぜひ話を聞きたい」という市議が何人も参加できなかったが、都議選候補者をふくめ、実際に有権者への伝達の最前線を担う人たちには、大いに参考になった。(「バッジをつけない主権者」としての伝達能力の向上も問われる) 今回の会場は、市ヶ谷事務所のすぐそばの私学会館であったため、講演会終了後は事務所にて、二次会を行った。いただきもののビールなどがあったため、会費は1000円。事務所は会議だけでなく、こんな使い方をすることもある。 | ||||||||||||||
| 「国民主権の再生としての創憲」 | ||||||||||||||
 3月15日 第45回東京・戸田代表を囲む会は、ゲストスピーカーに達増拓也・衆院議員をお招きして開催。達増議員は現在、民主党「次の内閣」文科大臣を務めるとともに、憲法調査会第一小委員会の委員長でもある。第一小委員会は「総論」「前文」を扱うところで、「自民党では中曽根さんがやっているようなところ」とは達増議員の弁。 3月15日 第45回東京・戸田代表を囲む会は、ゲストスピーカーに達増拓也・衆院議員をお招きして開催。達増議員は現在、民主党「次の内閣」文科大臣を務めるとともに、憲法調査会第一小委員会の委員長でもある。第一小委員会は「総論」「前文」を扱うところで、「自民党では中曽根さんがやっているようなところ」とは達増議員の弁。まず、19世紀=工業化前期、20世紀=工業化後期と人類史的な発展区分から、それぞれの時代の社会的対立、政治的変革、価値の源泉、人権の焦点、戦争のパターンなどを整理して、21世紀とはどういう時代か→そこで求められる憲法とは、というお話。 後半は、「創憲のポイント」として「自立と共生」をキーワードに、「国民主権の再生」「国民主権の発展」としてすべてをまとめあげるということが示された。 (3/17日経新聞によれば、翌日=3/16の小委員会で、前文に「天皇は国民主権の象徴」と明記する方針を決めた、とのこと) 「自立と共生で自由な主体性を発揮する主権者の歴史的発展」という創憲の基本理念は、「近代の総総括」「地球共生国家日本」という、「がんばろう、日本!」国民協議会の理念と大いに共振するものである。 達増議員は教育についても、自民党が「愛国心」を掲げるなら、民主党は「主権者を育成する」ことを教育の柱にすえると、明快に述べた。 (詳細は「日本再生」312号に掲載) | ||||||||||||||
| 「選挙後のイラク情勢と日本」 | ||||||||||||||
 2月28日、第44回の東京・戸田代表を囲む会は、大野元裕・中東調査会上席研究員
をお招きした。 2月28日、第44回の東京・戸田代表を囲む会は、大野元裕・中東調査会上席研究員
をお招きした。1月30日、「見切り発車」という形ではあったが、今年末の正式政府樹立にむけ、イラクで選挙が行われた。結果はボイコットしたスンニ派が惨敗、シーア派が多数派を占めるなかで、クルドが発言権を確保した形になり、国づくりは新しい困難と課題に直面している。 大野氏は、「イラクにおける民主主義の発展」という観点から問題を整理し、ここまでの問題点としては、アメリカによる民主化の「押し付け」が逆に、イラク人の民主主義の芽を押さえつける結果になっていることを挙げた。そして今後のポイントとして、アメリカ軍の掃討戦が行われたサドル・シティーの例をあげ、停戦(治安)には力が必要だが、力だけでは無理で、ここに復興(イラク人による/アメリカ企業の下請けではなく)と、さらに住民参加(国民参加)があれば、イラクの復興と安定は可能であると述べた。(サドル・シティー:シーア派強硬派といわれるサドル氏を支持する貧困地域。アメリカ軍の掃討戦の対象とされ激しい戦闘が行われ、一時は全土に非常事態が宣言された。停戦が実現した後、復興と住民参加によって、事態は安定化している。大野氏「衝突の拠点が安定のヒントとなるかもしれない」) イラクと聞くと、「イスラムだから民主主義になじまない」「部族社会だから民主主義は難しい」という偏見が日本人には少なからずある。こうした偏見をまず捨ててもらいたいと、大野氏は冒頭で述べたが、「民主制度の発展」という観点から物事を見るためには、類似性・同質性からではなく、方向性・志向性から物事を判断し、人間関係をつくるという訓練が必要である。その欠如や弱さから、冒頭のような偏見が大手を振ることになると、そろそろ気づくべき時だろう。 ライブドアとニッポン放送・フジテレビ、どう見ても後者のほうが類似性・同質性にしがみついているとしか見えないではないか。 (詳細は、「日本再生」312号に掲載) | ||||||||||||||
| 「第7回埼玉・戸田代表を囲む会」 | ||||||||||||||
 本年最初となった第7回埼玉・戸田代表を囲む会は、2月21日越谷中央市民会館で「通常国会の攻防戦と政権交代への道筋」をテーマに開催され、県下地方議員や市民等20数名が参加した。 本年最初となった第7回埼玉・戸田代表を囲む会は、2月21日越谷中央市民会館で「通常国会の攻防戦と政権交代への道筋」をテーマに開催され、県下地方議員や市民等20数名が参加した。ゲストスピーカーは、民主党東京都連幹事長の手塚仁雄衆議員で、手塚議員は先の参議院東京選挙区で2名当選を勝ち取り、7月の都議会議員選挙では21名の現職から50名の候補擁立と当選のための陣頭指揮にたっている。 講演では「政権交代にむけ次第に県連の強化、国会対策、各種団体対策、政策などそれぞれの議員が役割分担し民主党内のチームとして連携を強化している。また都議選ではすでに公認は44名に達しており最終的には51名の擁立を目指している。当然現職との調整やハレーションは避けられないが、首都東京での勝敗は国政選挙、取り分けて政権交代への大きな影響力となるため泥をかぶってもやり抜く。さらに政策はマニフェスト選挙に注目が集まりつつあり、東京マニフェストを5月に発表するが国政のイメージで作成する。本来首長選挙での政策集としてのマニフェストだが今回都議選で民主党が躍進し、2年後の東京都知事選勝利で具体的に実現していきたい。その時は石原都知事とは対決していくことになる」と党内マネージメントと権力闘争の明確なロードマップを提起した。  代表からは「政権獲得のための都議選を戦うことを、民主党が政権をとるという意味で準備しているのとそうでないのでは見方が全く違ってくる。小泉政権は外交も国政もすべてのことが政権延命のためだけにやっている。小選挙区制の導入は官僚内閣制から議員内閣制に変え政党、政策本位を進めていくことになった。マニフェストの政治文化を定着させなければならない。これはパーティマニフェストとローカルマニフェストのリンケージであり、先進自治体では予算の仕分け作業に取り組んでいるが、そもそも多くの首長や地方議員は予算そのものを組んだ経験がない。首長選挙という権力闘争に対して他人称での政策論や仕分け作業をするのは無党派主義である。このこととの戦いつまり政策で人間関係を作り変えるマネージメント能力を問われている」とコメントがあった。 代表からは「政権獲得のための都議選を戦うことを、民主党が政権をとるという意味で準備しているのとそうでないのでは見方が全く違ってくる。小泉政権は外交も国政もすべてのことが政権延命のためだけにやっている。小選挙区制の導入は官僚内閣制から議員内閣制に変え政党、政策本位を進めていくことになった。マニフェストの政治文化を定着させなければならない。これはパーティマニフェストとローカルマニフェストのリンケージであり、先進自治体では予算の仕分け作業に取り組んでいるが、そもそも多くの首長や地方議員は予算そのものを組んだ経験がない。首長選挙という権力闘争に対して他人称での政策論や仕分け作業をするのは無党派主義である。このこととの戦いつまり政策で人間関係を作り変えるマネージメント能力を問われている」とコメントがあった。閉会のあいさつに立った中村所沢市議は「よく右肩上がりといわれるが、自分達は全く実感がない世代だ。しかし人口減少時代と右肩上がりの違いをキチンと伝える能力が必要であり、理と情が極めて重要だと感じた」と締めくくった。 | ||||||||||||||
| 「ちば地域議員フォーラム・講演会」 | ||||||||||||||
 2月5日、千葉県白井市において、「がんばろう、日本!」国民協議会・千葉議員フォーラムによる講演会が開催された。テーマは「『三位一体改革』の鍵を握る、自治体の事業仕分け」、講師は「構想日本」の政策ディレクター・冨永朋義氏である。 2月5日、千葉県白井市において、「がんばろう、日本!」国民協議会・千葉議員フォーラムによる講演会が開催された。テーマは「『三位一体改革』の鍵を握る、自治体の事業仕分け」、講師は「構想日本」の政策ディレクター・冨永朋義氏である。「三位一体改革」は本来、自治体財政自立改革とでも言うぺきものであるが、実態は国の赤字を地方に付け回すものとなっていおり、「赤字予算」を組まざるをえない自治体が続出している。国は地方に赤字を付け回すことができるが、基礎自治体は逃げ場がない。本当にやるべき事業はなにか、どういうやり方がいいのか、こうした問題を考えていくうえでの前提となるのが、「自治体の事業仕分け」である。 ちば地域議員フォーラムは、自治体議員のネットワークで地域を変え、日本再生の底力をつくりあげようというもので、千葉・戸田代表を囲む会の活動のなかから、会員の地方議員が結成したもの。  白井市からは公務で出席できなかった市長に替わり、助役と市の政策立案に関わる幹部職員が10名程度参加(呼びかけ人の江田健治氏は白井市議会議長)。また近隣の市町村からも首長、議員・議会副議長、幹部職員など30名ほどが参加した。また「バッジをつけない主権者」も、千葉県下の会員のほか、JC関係者など30名ほどが参加。 白井市からは公務で出席できなかった市長に替わり、助役と市の政策立案に関わる幹部職員が10名程度参加(呼びかけ人の江田健治氏は白井市議会議長)。また近隣の市町村からも首長、議員・議会副議長、幹部職員など30名ほどが参加した。また「バッジをつけない主権者」も、千葉県下の会員のほか、JC関係者など30名ほどが参加。具体的には、新潟市と新潟県の「事業仕分け」の事例にふれながら、実際のしわけの仕方や考え方のポイントを説明。また、実際に「成人式」について、会場の来場者に仕分けを挙手でしてもらうなども行った(ほとんどの人が「成人式」自体は必要だが、自治体がやる必要はないとの考えだった)。 質疑応答では、実際に基礎自治体の予算作成や政策立案に携わっている立場から、実践的な質問が多数出て、また「事業仕分け」についても実際にやってみようという声が、首長からもあがっていた。 「バッジをつけない主権者」も、「市町村や県、国の役割の違いがなんとなくわかった。」「難しい話だが、全然眠くならなかった。」「自分の町もやって見たら良いのに」という反応で、かなりテクニカルな話にもかかわらず、集中して聞いていたようだ。 このようなレベルの高い講演会にも、それなりの関心を持って、「バッジをつけない主権者」が参加していること自体が、自治体を取り巻く環境が確実に変化していると感じる。今までのような「観客民主主義」「おまかせ民主主義」ではなく、確実に政治や行政に対して、モノ申す人が増えている。「バッジをつけた主権者」は今までのような感覚で政治を行うのではなく、このような意識の高い「バッジをつけない主権者」との協働をつねに視野に入れて行動すべきであり、それこそが真の意味での「民主主義」の再生であることを再確認した講演会であった。 また、「がんばろう、日本!」国民協議会の千葉県逆マニフェスト検討グループでは、この間県知事選挙にむけた「逆マニフェスト」を検討してきたが、2月10日、県庁記者クラブで発表、同時に現職の堂本知事と予定候補にこれを届けた。 逆マニフェストについては、「がんばろう、日本!」国民協議会のホームページに掲載。 | ||||||||||||||
| 「政権交代の一点にしぼった政策論争の展開を」 | ||||||||||||||
 2月1日第43回東京・戸田代表を囲む会。ゲストスピーカーは、民主党政調会長代理の古川元久衆院議員。 2月1日第43回東京・戸田代表を囲む会。ゲストスピーカーは、民主党政調会長代理の古川元久衆院議員。古川議員は、スイスで行われているダボス会議から帰国したばかりということもあって、ダボスの報告からお話を始めた。 五年前から毎年参加しているが、年々日本の存在感は低下の一途。今年は中国からは外相、副首相が参加するなど、「東アジアは中国」という流れができている。日本はかつては「経済」で存在感を示せたが、これからはそうはいかない。経済以外で存在感を示すにはどうするか? その点でいうとヨーロッパの智恵に学ぶところは大きい。アメリカに対して「力」ではなく、「構想力」「論理力」でアジェンダ設定をリードしている。 政策論戦の進め方については、相手(与党)の土俵に乗った論戦ではなく、こちらからアジェンダ設定をしていく、これがどこまでできるかが勝負。すべてを「次の選挙で政権交代」というところにむすびつける。そのために・・・というところから設定していく。これが基本的な構え方。 焦点は引き続き「年金」。与野党協議に応じるかどうかのポイントは、与党に本当にやる覚悟があるか。つまり「次の選挙で争点にさせない、その口実のための先延ばし」なら、応じない。協議に応じるということは、われわれも争点にできないということだから、期限を切って結果を出すという覚悟が与党になければ乗れない。このままの状態で、次の選挙の時に「与党は無責任だ」と批判するのは気楽だが、それでは責任政党とはいえないので、与党が真剣に協議するなら喜んで応じる。 ポイントは、協議のすべてをオープンにする「透明性」と、事務方を霞が関の官僚にやらせない、この二点が担保されるか。これが与党の「真剣さ」を測る物差し。 郵政改革については、改革の本質は「郵便事業」ではなく、財政・金融問題。このままでは巨額の郵貯・簡保の資金は、自力では運用できない以上、委託することになり、外資も含めた「手数料稼ぎ」の草刈場になりかねない。まずは、ここの規模縮小をやらないと、次へ進めない話。 郵政については、対案というよりも基本的な考え方を示すことになると思う。 今回も民主党独自の予算案を作成。大きなポイントは、子ども、若者に重点的に配分。子ども手当ても「バラマキ」と受け取られるかも知れないが、扶養控除などをなくして財源を確保し、直接、子どもに対していくら、という形にした。次の総選挙に向けて、子どもにフォーカスを当てていく。 自民党は、郵政の次は憲法だ、教育基本法だと言っているが、われわれはもっと地に足のついたところで、きちんとした論議をして、政策を積み上げていきたい。 民主党に問われているのは、「政権を任せても大丈夫」という信頼感、安心感をいかに国民のなかに定着させていくか、という点。ここにポイントをしぼってやっていく。 | ||||||||||||||
| 「第5回 関西『戸田代表を囲む会』報告」 | ||||||||||||||
 1月30日京都で、第5回関西「戸田代表を囲む会」を開催。
ゲストスピーカーの尾立源幸・参議院議員から、議員半年間の教訓と通常国会に臨む姿勢として、「二大政党制の中で大切なことは、相矛盾する意見を表に出して、議論の過程までを説明する政治の責任。国民に考えさせない、選択肢を与えない”依存と分配”の政治文化を打破したい」と報告。
討議に入り、戸田代表より「経済活動の領域でも、リスクをとる、主権者意識持つものができ、『依存と分配vs自立と創造』の亀裂が入った(民主党の団体交流の対象=政治市場の変化)。自民がだめだからでなく、そもそも論つまり今までの過程を綱領的価値観と戦略から再設計すべきだ、という政治市場が生まれた。次の時代までをとらえるマニフェストへの再設計が必要」と方向が示されたあと、木村正治・民主党東大阪市議、佐々谷元秀・民主党京都口丹波支部長、北神圭朗・民主党京都府4区総支部長、山下まさし・民主党亀岡市議、畑口欣也同人(小豆島在住・農園経営)、上野賢一郎・自民党滋賀県1区総支部長(総務省出身・39歳)から、各々各地でのマニフェスト政治文化を定着させ、「新たな公共性」を打ち立てていく活動の報告と「あろうべき国のかたち」への思いが語られた。 1月30日京都で、第5回関西「戸田代表を囲む会」を開催。
ゲストスピーカーの尾立源幸・参議院議員から、議員半年間の教訓と通常国会に臨む姿勢として、「二大政党制の中で大切なことは、相矛盾する意見を表に出して、議論の過程までを説明する政治の責任。国民に考えさせない、選択肢を与えない”依存と分配”の政治文化を打破したい」と報告。
討議に入り、戸田代表より「経済活動の領域でも、リスクをとる、主権者意識持つものができ、『依存と分配vs自立と創造』の亀裂が入った(民主党の団体交流の対象=政治市場の変化)。自民がだめだからでなく、そもそも論つまり今までの過程を綱領的価値観と戦略から再設計すべきだ、という政治市場が生まれた。次の時代までをとらえるマニフェストへの再設計が必要」と方向が示されたあと、木村正治・民主党東大阪市議、佐々谷元秀・民主党京都口丹波支部長、北神圭朗・民主党京都府4区総支部長、山下まさし・民主党亀岡市議、畑口欣也同人(小豆島在住・農園経営)、上野賢一郎・自民党滋賀県1区総支部長(総務省出身・39歳)から、各々各地でのマニフェスト政治文化を定着させ、「新たな公共性」を打ち立てていく活動の報告と「あろうべき国のかたち」への思いが語られた。
 最後に戸田代表から「国民が問うているのはマニフェストの実現能力。学会の力を借りずにきた部分を、改革保守のコアまでの脱皮を急がせるためにも、政権交代が必要」「国民国家の相対化は主権在民の徹底化、国家主権のEUへの部分移譲と基礎自治体への移譲は同時進行。各々が述べた日本における民主主義のありよう、パブリックとは何かを形にするため、知恵と情理を尽くす活動が問われる」とまとめの提起があった。
関西では、4月24日に「第10回関西政経セミナー」を村田晃嗣・同志社大学助教授(米外交・政治史)を講師に迎え開催する。 最後に戸田代表から「国民が問うているのはマニフェストの実現能力。学会の力を借りずにきた部分を、改革保守のコアまでの脱皮を急がせるためにも、政権交代が必要」「国民国家の相対化は主権在民の徹底化、国家主権のEUへの部分移譲と基礎自治体への移譲は同時進行。各々が述べた日本における民主主義のありよう、パブリックとは何かを形にするため、知恵と情理を尽くす活動が問われる」とまとめの提起があった。
関西では、4月24日に「第10回関西政経セミナー」を村田晃嗣・同志社大学助教授(米外交・政治史)を講師に迎え開催する。
がんばろう、日本!国民協議会・同人 杉原卓治 | ||||||||||||||
2004/5~2004/12の《日記》はこちら| 2003/9~2004/4の《日記》はこちら | 2003/2~2003/9の《日記》はこちら | 2002/7~2003/1の《日記》はこちら | 2001/11~2002/5の《日記》はこちら | |||||||||||
 はじめに木村正治同人(民主党・東大阪市議)より主催者挨拶のあと、「青年学生
読者会」の青木純平幹事から「日本人に足りない力」と題して、コミュニケーション
力の源泉は歴史と未来に対する責任(インテリジェンスと想像力)にあるとの問題提
起があり、これを受けるかたちで、村田晃嗣・同志社大学教授、松井孝治・民主党参
議院議員、福山哲郎・民主党京都府連会長・参議院議員からコメントをいただいた。
はじめに木村正治同人(民主党・東大阪市議)より主催者挨拶のあと、「青年学生
読者会」の青木純平幹事から「日本人に足りない力」と題して、コミュニケーション
力の源泉は歴史と未来に対する責任(インテリジェンスと想像力)にあるとの問題提
起があり、これを受けるかたちで、村田晃嗣・同志社大学教授、松井孝治・民主党参
議院議員、福山哲郎・民主党京都府連会長・参議院議員からコメントをいただいた。 村田教授は「古典と歴史から学ぶことの重要性」を説かれ、「私もこれから三十七
年間、毎年二冊の古典を読むことを自らに課している」と披瀝された。松井議員から
は「想像力を持てる国家づくり」の大切さが、福山議員からは「環境問題とは、地球
の裏側と五十年後への想像力」との考えがそれぞれ述べられた。
村田教授は「古典と歴史から学ぶことの重要性」を説かれ、「私もこれから三十七
年間、毎年二冊の古典を読むことを自らに課している」と披瀝された。松井議員から
は「想像力を持てる国家づくり」の大切さが、福山議員からは「環境問題とは、地球
の裏側と五十年後への想像力」との考えがそれぞれ述べられた。 つづいて、同人の隠塚功・民主党京都市会議員(左京区選出)、山下雅史・民主党
亀岡市議会議員から、京都二区(前原誠司代議士=祝電メッセージを披露)、京都四
区(北神圭朗代議士)での活動の現状と課題が、同人で民主党の佐野英史・奈良県三
郷町議会議員から地域主権の戦いの報告が、それぞれなされた。また、北神圭朗衆議
秘書の片桐直哉氏、尾立源幸参議秘書の金子裕伸氏からも挨拶をいただいた。
つづいて、同人の隠塚功・民主党京都市会議員(左京区選出)、山下雅史・民主党
亀岡市議会議員から、京都二区(前原誠司代議士=祝電メッセージを披露)、京都四
区(北神圭朗代議士)での活動の現状と課題が、同人で民主党の佐野英史・奈良県三
郷町議会議員から地域主権の戦いの報告が、それぞれなされた。また、北神圭朗衆議
秘書の片桐直哉氏、尾立源幸参議秘書の金子裕伸氏からも挨拶をいただいた。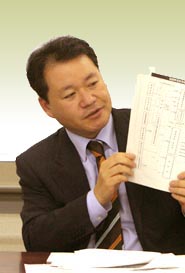 堺市長選挙にマニフェストをかかげ挑戦し、惜敗した森山浩行・前大阪府議(同人)の報告のあと、尾立源幸・参議院議員から「これからの政党マネジメントと民主党」と題し、党改革の緊要の課題として党本部(職員)改革が語られた。民主党兵庫9区総支部長・畠中光成同人、同東大阪市議・木村正治同人からの発言がつづき、戸田代表から
堺市長選挙にマニフェストをかかげ挑戦し、惜敗した森山浩行・前大阪府議(同人)の報告のあと、尾立源幸・参議院議員から「これからの政党マネジメントと民主党」と題し、党改革の緊要の課題として党本部(職員)改革が語られた。民主党兵庫9区総支部長・畠中光成同人、同東大阪市議・木村正治同人からの発言がつづき、戸田代表から 「マニフェストで立候補するとは、次の四年間も市長候補を続けること」「党改革が民主党でも総選挙候補者や地方議員レベルでリアルな課題になった」とコメントがあった。懇親会には、長尾敬同人・民主党大阪14区総支部長も参加。「反転攻勢」に向けた決意が述べられた。
「マニフェストで立候補するとは、次の四年間も市長候補を続けること」「党改革が民主党でも総選挙候補者や地方議員レベルでリアルな課題になった」とコメントがあった。懇親会には、長尾敬同人・民主党大阪14区総支部長も参加。「反転攻勢」に向けた決意が述べられた。