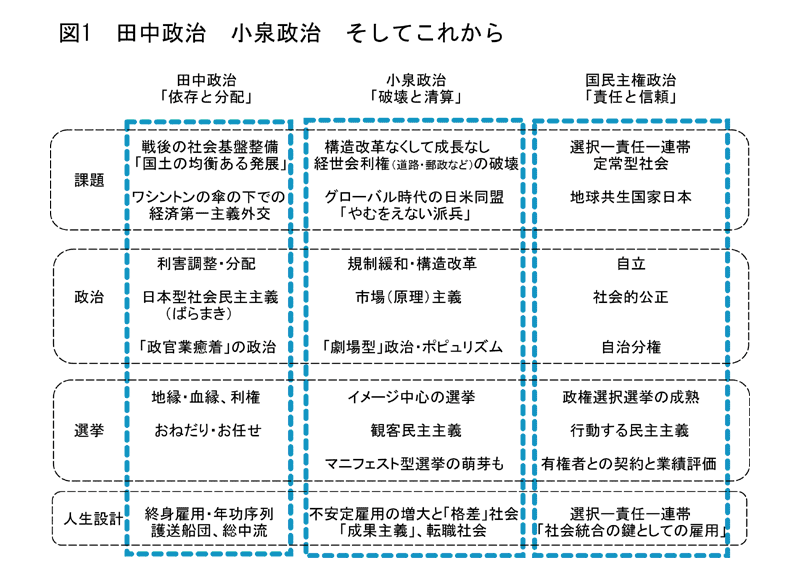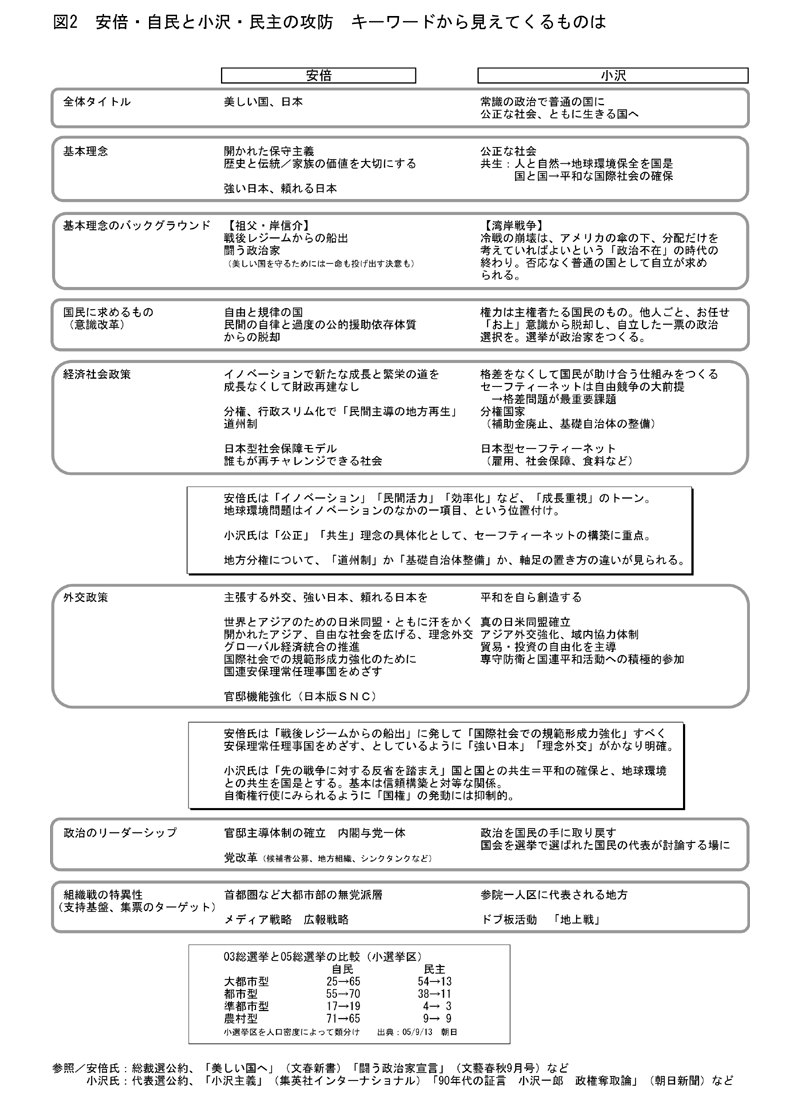|
日本再生 329号 2006/10/1発行
独立変数としての主権者運動の問題設定から安倍・自民と小沢・民主の攻防を、 国民主権の「共有地」をさらに発展させるためにつかいこなそう | ||
| 劇場型政治の終わり 官邸主導は個人技からチームプレーに ―次期政権選択選挙に向けた攻防の幕は切って落とされた
「論功行賞」「派閥均衡」「仲良し内閣」。安倍政権に対するこうした評価は、評論としてはそれぞれ当たっているだろう。しかしここから国民主権の深まりが触発されるかといえば、答えは明らかにノーだ。 |
安倍政権の人事(党、内閣とも)は、これをよくあらわしている。「仲良し内閣」「論功行賞」と言うが、第一に、補佐官や党役員の配置にみられるように、官邸主導が個人技からチームプレーとなったことが見てとれる。第二に、誰をどのポストに就けるかということから、「この内閣が何をどのようにやろうとしているか」という意思が伝わってくる。後は政策イシューのマネジメント、政権運営のハンドリングがこの体制でどこまで、そしてどのように機能するか、であろう。 半年前には、同じく戦後生まれの前原氏が民主党代表となり、「仲間」を集めて執行部をつくり、理念先行型の党運営を行おうとして躓いた。他山の石とすべし、だろうが「テレビ政治」に足をすくわれる心配は、安倍政権の場合にはずっと少ないだろう。田中政治の「分配・調整」型でもなく、小泉政治の「対決型」でもない、権力をめぐる戦後世代のマネジメント能力が本格的に問われる。 官邸主導が制度化されるということは、議院内閣制の前提である内閣与党一体が「当然の日常」となることを意味する。言い換えれば、「抵抗勢力」に代表されるような与党内の対立劇が、政治ドラマの主役から退場することになる。(観客民主主義からすれば「政治がおもしろくなくなる」。) そこで二つのことを指摘したい。一つ目は、党内対立から政党間対立へと、政治の焦点が移っていくべきだということ。与党内対立が主役となることで、これまで脇役に追いやられていた野党の出番となる。十月の補選、来年の統一地方選、参院選を通じて「二大政党」の枠組みを再びリアリティーあるも | |
| のにすることができるかどうか。参院選に起死回生をかける民主党・小沢代表の問題設定は、ここに一定程度符号している。それを「小沢頼み」ではなく、組織的結束力としてどこまで発揮できるのかが、民主党の課題だろう。 同時に、政党間対立の中身である。与野党のあるべき対立は、与党は内閣の政策に責任を持ち、野党はそれを徹底的に検証する、というものである。現状分析、問題設定が違うのか、そこが同じでも優先順位が違うのか等、「論難」ではなく「討論」のあるべき姿に、どこまで近づくのか。与党が、実現もしていない野党の政策を批判する、というようなことでは「論難」のレベルだし、スキャンダル合戦のようなことをやれば、政治不信の泥沼で自滅することになる。 ただしここには大きな問題がある。党内対立から政党間対立へ、政権を争う二大政党の政党配置へ、という方向性は明らかであるが、足元では「マニフェスト『以前』問題」(政党の紀律化ができていない)が依然として残っているのも事実である。与党の場合には、曲がりなりにも官邸主導の制度化と政権運営として、日々この問題に具体的に対処せざるをえないが、野党の場合は与党を上回る工夫が必要なはずである。 主権者運動の問題設定からいえば、それを既存政党に期待するのは、そもそも「ないものねだり」であって、そのこと自体が独立変数たりえない(既存政党の従属変数でしかない)ことを意味する。「マニフェスト『以前』問題」とは、政党の側で言えば、マニフェストによる紀律化がまるでできていない、ということであるが、有権者の側では「政治を『面白いもの』として消費する」観客民主主義の問題である。既存政党に「ないものねだり」をするヒマがあれば、有権者として「観客民主主 |
義から脱却する」ための工夫をひとつでもしよう―これが主権者運動というものだろう。 自治の現場には、そのための材料も人の縁も、その気になれば見出せる(本号の各報告を参照)。国民主権の共有地を耕す活動を、まず始めよう。それにどう対応するのか、ここから既存政党を検証しようということだ。「主権は国民に存する」、「有権者の一票が政権のあり方を決める」、「たかが一票、されど一票」ということを、観客民主主義の余地を残したままでも「分ったふり」ができる、という空間は本当になくなる。 二点目は、内閣与党一体が当然の日常になるということは、「強い首相」が当たり前になるということだ(待鳥聡史「中央公論」10月号参照)。小泉総理は、抵抗勢力の存在とその個性とがあいまって、トップダウン・対決型の色合いが強かったが、安倍総理の場合にはホワイトハウス型のチームプレーを目指すのであろう。その場合でも、経済財政政策(消費税、社会保障費負担など)にしろ、安全保障(沖縄基地問題)にしろ、小泉政権が先送りした、国民負担をともなう難しい問題について、最終的な決定は総理が下すことになる。 「強い首相」とは、誰によって、どのような決定が行われたのかが見える、ということであり、政治決定に対して首相と内閣の責任が明確になるということである。このように「権力と責任の関係が明確になることは〜中略〜有権者にとって決して悪い話ではない」(前出・待鳥氏)。それは、「イメージで支持」「政策は期待しないが、政権は支持」という観客民主主義の気分、無責任な無党派心情を、有権者自身が「卒業」していくための足がかりとなりうるからである。 田中政治(依存と分配)に対する「破壊と清算」としての小泉 | |
| 政治は幕を閉じた。劇場型政治・観客民主主義から、「あろうべき国民主権の政治」へ向かうための「次」の舞台を準備する―これが安倍政権をめぐる攻防の政治性格である(図1参照)。安倍政権はまず「官邸主導を個人技からチームプレーへ」として、最初の一手を打った。小沢・民主党は、小泉政治の下で脇役に追いやられていた政党間対立を政治の主役にすべく、体制をとろうとしている。これら既存政党が、独立変数としての主権者運動が自らの持ち場で国民主権の共有地を耕すことに対して、どういう対応をとるのか(協働する、利害を共有する、食い散らす、かすりもしないetc)。ここから既存政党との距離感を測っていこう。
安倍・自民と小沢・民主の攻防を、
新政権をめぐる攻防の性格は、小泉政権の総括のなかにある。小泉政権の単純な全否定も単純な継承も、「失われた十年」にさらに五年間を付け加えるだけにすぎない。好むと好まざるとにかかわらず、小泉政権は政治の手法や政策において大きな転換を試みた。その遺産をどう整理するか、その視点によって、次の課題も方向性も異なってくるのは当然である。 |
「だれがやっても同じ」という政治不在の(政治意思なき)五十五年体制・田中政治の権力システムに替わって、「政権のあり方は有権者の一票が決める」という国民主権の権力システムをどうつくり上げていくのか。この歴史的過程の中で小泉政権を総括する場合と、それが抜けて小泉政権の是非をあれこれする場合とでは、見えてくるものがまったく違うのは当然である。前者の前提を欠いたまま、「格差社会」や「アジア外交」をポスト小泉の課題としていた場合には、安倍政権をめぐる対立軸はきわめて不毛なものになってしまう。 小泉政権の遺産が複雑なのは、一方で官邸主導・「強い首相」や「政権選択の瞬間的実感」を醸し出しながら、同時に(政党政治の基盤を掘り崩す)政治不信や無党派主義をテコにしてそれを行ったことによる。ポピュリズム批判は、国民主権が教科書から現実政治の課題になったことの裏返しの証左である。このネジレをどのように整理して、あろうべき政党間対立の姿―政権選択選挙を可能にする政党配置への「次の一歩」を準備するか。ここが安倍政権をめぐる攻防の最初の課題であり、その糸口とするべく安倍・自民と小沢・民主の攻防を使いこなす―これが独立変数としての主権者運動の問題設定である(図2の使い方)。 ここではその手がかりの一例として、「格差問題」の考察を試みる。 「小泉政権とその『改革』にまつわる認識は、これを悪しき市場主義の一例と捉えるのか、それとも、むしろ市場を疎外してきた非合理性の是正と捉えるのか、という点に大きな分岐点がある。それは、『格差拡大』の原因をどこに見るかの違いにもつながるものである。 前者の観点からすれば、『改革』は、市場原理の貫徹により、公的な福祉が削減され、『弱者切り捨て』をもたらしたのが | |
| 『構造改革』ということになる。これに対し、後者の観点は、旧来のシステムに由来する不平等が、『改革』を契機に減少し、市場という土台の上で、公平な競争状況が広がっていくことと見る。公的な規制の削減が、『自由競争による社会の最適化』を進めていく世界である」(高原基彰「論座」10月号) 現実がそれほど単純なものではないことは、高原氏自身が後述しているが、まずは視点の違いによって、小泉「改革」の評価と今後の課題が大きく違ってくるという意味は、この指摘からも分る。安倍・自民の「再チャレンジ」と、小沢・自民の「格差問題が最重要」というスタンスの違いは、こうした点からも見えてくる。しかし、これを「評論」として理解したつもりになっているかぎり、安倍・自民と小沢・民主の攻防(図2)を国民主権の深化のために使いこなすことはできない。 現実がそれほど単純なものではない、というのは、欧米においては「市場の失敗」と「政府の失敗」をめぐって、また市場と政府の役割や関係をめぐって、「自由主義・新自由主義」「社会民主主義・第三の道」あるいは「保守主義」による政府が構成されてきた(これらの「主義」をガイドラインとして国民が政府を作ってきた)のに対して、わが国ではこうした前提が欠けているからである。 例えば、「日本型福祉社会」(79年自民党)では、福祉国家の失敗といわれるイギリス病の轍をふまないために、終身雇用・年功序列を維持する企業と、家長の収入で家計を維持する核家族(サラリーマンの夫と専業主婦)からなる日本社会が構想されている(高原・前出)。いわゆる「日本型社会民主主義」の構造であるが、これが欧米的な社会民主主義とは理念的に異質であることは言うまでもない(欧米に発する社会民 |
主主義は、家族や企業という私的セクターに替わって、政府などの公的セクターが福祉を担うというのが基本的な発想)。 そうしたネジレを引きずったわが国の現実では、「『日本型福祉社会』の残滓と、否応なく進む『構造改革』とが組み合わさった時、双方の否定的要因が掛け合わされた状態になること」が危惧されると、前出の高原論文は指摘する。 例えばそれは、日本型福祉の根幹をなす「終身雇用」や「年功序列」といった既得権を批判しつつ、しかし正社員願望にしか人生設計を託すことができないという若者の状況にみられる。「既得権」への反感や、旧来の分配にあずかれないかもしれないという不安が、堅固な正社員システムという旧来の認識を逆に強化している、と高原氏は指摘する。 しかし、日本型福祉の基盤たる家族も企業も、すでに崩壊している。(安倍政権が「家族の価値を大切に」とどんなに叫んでも、旧き良き家族をスタンダードモデルとして復元することは不可能だろう。)にもかかわらず、旧来の家族・労働モデルが価値あるものとして残りつづければ(それを前提に政策対立が構築されれば)、そこに生まれるのは、ともに市場に参加して「能力を発揮し、やりがいを感じる」ことができる「勝ち組夫婦」であり、フリーター夫婦との格差は、さらに広がっていくことになる。これが高原氏の指摘である。 安倍・自民と小沢・民主の「格差問題」に対するスタンスの違いを、評論で分ったつもりになっていたのでは、国民主権の深化に向かってノミのひと跳ねさえしない、というのは、ここの問題である。雇用や人生設計をめぐる問題―いわゆる「格差問題」の重要な側面―を、終身雇用を守るvs何度でもチャレンジできる、という平面的な(現実には存在しない)対立軸 | |
| で分ったつもりになるために図2を使うのではなく、こうした「疑似」対立軸の前提となる現実をまずとらえ、そこでの問題設定を共有するために図2を使う。その工夫と試行錯誤のなかからこそ、「次」への道が準備されるはずだ。 ちなみに高原氏は、あろうべき方向として「社会統合の鍵としての雇用」という問題提起をしているが、それはわれわれにとっては「天の声」としての「正解」ではなく、主権者としての前述のような現実との格闘のなかからこそ見出されてくるものであろう。 同様に「地方格差」についても、安倍・自民と小沢・民主の政策対立の構図が、民間活力vs「バラマキ」というレベルになるとすれば、どういう社会層をその支持基盤とすればそうなるのか、どういう社会層を支持基盤にした場合には、「分権・自立」への媒介となるのか、という現実の組織戦にのみかかっている。 橋本政権から公共投資は減りつづけ、小泉政権の最後には5パーセントを切っている。つまり「日本型社会民主主義」の一要素であった「公共事業による雇用対策」が、ほとんど意味をなさなくなっている。公共事業への依存度が高い地方には、打撃であることは事実だ。 同時に、「分権」の名の下に地方に対する補助金や交付金は次々にカットされ、財政運営を国からの支援に依存する地方には、これも打撃になっている。言い換えれば、こうしたなかで「お上」をあてにせず、自分たちで知恵を出して自立しようとする地域(自治体、事業体、住民)と、「お上」頼みを続けようとする地域(自治体、事業体、住民)との主体上の格差が鮮明になっているということだ。このどちらに立脚しようとするか、それによって民間活力vs「バラマキ」というレベルに終わるのか、それとも「次」へのステップとなるかが決まる。 |
〇七年統一地方選におけるローカルマニフェストの取り組みは、現に生まれている自治分権のさまざまな主体を、「次」へのステップを踏み出す再編の力として加速的に開花させる舞台として位置付けられるものである。そのために図2を使いこなす工夫と試行錯誤を重ね、その実践的教訓を交流、蓄積していこうではないか。
「守るべきもの」はあるか
安倍政権は自ら「開かれた保守主義」と称している。それに対して民主党は、「岸・安倍=親米保守に対して、(軽武装・経済重視の)保守本流こそ小沢・民主だ」という。この構図をそのまま受けとって評論しても、主権者運動にはかすりもしない。 | |
| 伝統主義でもなく、不可逆的な変化を無理やり元に戻そうとする反動思想でもなく、普遍的な観念を掲げて現状を一挙に変えようとする革命主義でもなく、むしろ時代に合わせて現状を常に変えていくことでしか体制を維持することはできない、というのがバークに代表される保守主義の基本的な発想である。 従って「変える」ためには「変わらぬもの」「守るべきもの」が明確でなければならない。ここをこそ問うべきであろう。「失われた十五年」のなかに、あるいは「戦後六十年」のなかに、「守るべきもの」はあるのか。あるとすれば、それは何か。あるいは戦後六十年の否定の上に「革命」をやるのか。(「占領憲法の否定」の上に改憲を論じるという論理なら、まさに革命であり、東京裁判の否定から靖国を論じるなら、それも革命であろう。こういう論理的帰結を意味することを情緒や心情で語るのは、扇動家であって政治家ではないし、まっとうな主権者でもない。) 「守るべきもの」があるとすれば、それは国民主権である―これが独立変数としての主権者運動だ。小選挙区導入以来、小泉政権をめぐる攻防を媒介に、そして決定的には地方自治の現場において、国民主権の「守るべきもの」が具体的にあるからこそ戦う、という主権者(バッジをつけた主権者、バッジをつけない主権者)が生まれてきている。これがわれわれの「共有地」にほかならない。 安倍・自民、小沢・民主に「守るべきもの」はあるか、それは何なのか。自治の現場では、国民主権の実際が隠しようもなく洗われる。情緒や屁理屈で分ったフリはできない。ここで「守るべきもの」がどれほどあるのか。しっかりと見定めていこう。 |
(注) エドマンド・バーク:1729〜1797。イギリス保守主義を代表する政治思想家。『フランス革命の省察』は普遍主義による急進的な革命(フランス革命)を批判して、歴史的に継承されていくものの上に変革を論じたもので、近代保守主義の原点とも言われる。 フランス革命の人権宣言は「人の生まれながらの時効にかからぬ権利」と謳ったが、バークはそれに真っ向から反論して、あらゆる権利義務は歴史的に形成され継承されるものであり(「時効取得的」=プレスクリプティヴであり)、それは国制や習慣と結びついてはじめて存立しうるとした。すべての権利と自由は過去の伝統に由来するが、これを保持するには現在および将来にわたる努力が必要であり、時代の変化に合わせて変えていくことなしに伝統は保持できない、というのがバークの立場。 下院議員としての経歴を有し、野党の代表的論客でもあったバークは、イギリス王制の専制政治を批判、アメリカ植民地紛争についても茶税の廃止などを早くから主張したが、これも「自然権」のような普遍的観念によるものではなく、アメリカ人の権利はイギリス帝国の構造において歴史的に認められるべきものであり、本国議会が直接植民地に課税することのほうが、英国国制の変更であること、そして遠く離れた植民地を直接統治することは不可能で、これに固執すべきでないという便宜的判断によるものであった。 | |